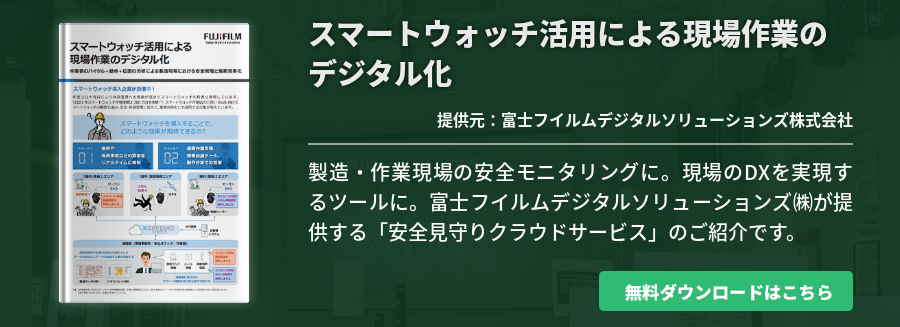製造現場における重大な事故は「二度と起こさない」ではなく、「徹底的な予防」が肝心です。そのために日常的なヒヤリハット防止活動は欠かせません。本記事では、ヒヤリハット防止活動の進め方や効果的な取り組み、マンネリ化防止のコツについて解説します。ITツールによるおすすめの対策も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ヒヤリハットとは
「ヒヤリハット」とは、労働中に生じる、重大な事故につながりかねない事象のことです。「ヒヤリとした」「ハッとした」という場面であることから「ヒヤリハット」と呼ばれます。ヒヤリハットは、労働災害が重大な事故に至りやすい製造現場や医療現場などで大きな問題となっています。製造現場は大型機械を用いることが多く、医療現場は人命に密接に関わるというのが、これらの現場でヒヤリハットが大きな問題とされている理由です。
大きな労働災害を未然に防ぐには、ヒヤリハットの段階で対処する必要があります。事故発生についての経験則である「ハインリッヒの法則」は、ヒヤリハットを防ぐうえで欠かせない知識です。アメリカの損害保険会社で働いていたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが1931年に提唱したもので、「1:29:300の法則」とも呼ばれます。1件の重大災害の背後には29件の軽傷災害が潜み、さらには実際に災害には至らなかった300件のヒヤリハットが発生しているというものです。1951年に日本で知られるようになって以降、現代まであらゆる現場において注意喚起に活用されています。
そもそもヒヤリハットはなぜ起こる?
ヒヤリハットを減らすには、そもそもヒヤリハットが起きる原因を知ることが重要です。ヒヤリハットの発生にはさまざまな原因がありますが、代表的なものをいくつか紹介します。
- 作業への不慣れ
作業に関する知識・経験が不足していたり、危険性の認識が曖昧だったりした場合に、事故につながる可能性が高まります。特に、仕事をはじめたばかりの新人によく見られます。 - 油断
実は最も事故が起きやすいのが、作業に慣れはじめて油断した頃合いです。何十年もの経験を持つベテランであっても、危険性を軽視したり、効率を優先したりすることで、事故に至ることがあります。 - 思い込みによる判断ミス
これまでの経験から作業手順の必要性を自己判断し、本来必要な手順を省略してしまうことにより、事故の発生リスクが増加します。特にベテランの従業員が陥りやすい失敗です。 - 焦り・パニック
なんらかのアクシデントが発生して正常な判断ができなくなると、普段ならあり得ない行動を取ってしまう可能性があります。 - 疲労
長時間作業を続けていると、疲労によって判断力が低下してしまいます。さらに、疲労によって思い通りに身体が動かなくなることも事故につながります。 - コミュニケーション不足
聞き違いや認識のずれ、また連絡不足などがあると、誤った作業が発生する可能性があります。誤った作業をしている従業員への注意喚起がしづらいような雰囲気の現場は、さらに危険です。これらはいずれも、上下間や従業員間のコミュニケーション不足が原因です。
上記のように、ヒヤリハットは新人からベテランまで、作業に対する慣れや知識の多寡にかかわらず起こり得ます。いずれも人為的ミスだと思われるかもしれませんが、不十分な管理体制や脆弱なフォロー体制などが問題です。従業員に一任することなく、会社として改善に取り組むことが重要です。
製造業の工場におけるヒヤリハットとは
製造業の工場には、大型機械や重量のある資材が置かれているほか、フォークリフトなどの運搬用車両が走っています。使い方を誤ったり、安全確認を怠ったりすれば、重大な事故につながりかねません。製造現場には事故の発生要因となるものが多く、ヒヤリハットによる事故が起きた場合には、従業員が大けがを負うだけではすまず、最悪の場合には死亡に至ることもあります。ひいては企業の運営に関わるため、危険の芽をひとつずつ摘み取り、事故を未然に防がなくてはなりません。
そのため、工場内ではさまざまな安全対策が取られています。作業者に対しては常に安全確認が励行され、機械や車両などを使用する際には、手順にしたがった正しい使い方をするよう喚起しています。工場内に立ち入るすべての従業員・関係者がヘルメットを被っていたり、工場内のあちこちに標語が貼り付けられていたりするのは安全対策の一環です。
そのほかにも製造業の工場では、ヒヤリハットを発生させないために、安全点検チェックシートの記入、抜き打ち検査、5S活動(整理、整頓、清掃、清潔、しつけ)などに取り組んでいます。
製造業の工場におけるヒヤリハットの事例
実際にあった事例を知れば、ヒヤリハットに対する有効な施策を立てやすくなります。厚生労働省のサイトに掲載されている事例とその対策を簡単に紹介します。
ヒヤリハット事例1. 作業場での激突
1件目の事例は、食料品製造業における市場内荷卸しの最中に起きたものです。作業場内で、方向転換のためにフォークリフトをバックさせたところ、後方にいた作業員とフォークリフトとが激突しそうになりました。
この事例での問題は、作業員がフォークリフトの作業場へ自由に立ち入れてしまう現場環境にあります。対策としては「フォークリフトの作業場には労働者を立ち入らせない」「フォークリフトの作業計画を定め、運行時には誘導員を配置する」などが考えられます。
ヒヤリハット事例2. 作業中のはさまれ・巻き込まれ
2件目の事例は、金属プレス製品製造業におけるボール盤での穴あけ作業中に起きたものです。ボール盤でステンレス板に穴を空ける作業をしていた作業員が、ボール盤台上にある異物を手袋をはめたまま片手で取り除こうとしたところ、回転中のドリルに手袋が巻き込まれそうになりました。
この事例は、作業者の油断や慣れによって発生しています。もともと作業上のルールとして存在していたはずの「ほかの作業を行う際には、必ずボール盤の電源を切る」「不要なものは盤台上に置かない」「巻き込まれるおそれのある手袋は外し、作業は素手で行う」ということをあらためて徹底させる必要があります。
ヒヤリハット事例3. 熱中症
3件目の事例は、炎天下で作業を行い、終業後に具合が悪くなったという事例です。近年、夏場には連日のように猛暑が続き、熱中症に関する報道や注意喚起を耳にします。屋内にいるから安心というわけではなく、工場内での作業にも熱中症のリスクが潜んでいます。
特に規模の大きな工場の場合、作業場所によっては極端に体感温度が低い場所もあれば、日差しが差し込んできて、温度が高い場所もあります。工場内全体で熱中症の発症を抑えるために、温度管理を徹底して行うことが重要です。温度管理のほかに、適宜涼しい場所での休憩や水分・塩分補給も心がけなくてはなりません。
厚生労働省が公表した「令和4年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」によれば、発生場所が工場とは特定されていないものの、2022年の製造業の熱中症による死傷者数は145人で、うち2人が死亡しています。全業種では、2022年の職場での熱中症による死傷者数は827人(うち30人が死亡)でしたが、製造業は建設業の179人についで多い業種となっています。
例えば夏場には、暑さ対策としてエアコンの効いた休憩場所を整える、適切な服装やドリンク類を用意するなどの対策を取る必要があります。暑さ指数や個々の健康診断結果などをもとにした、適切な作業管理も欠かせません。
ヒヤリハットを減らす効果的な3つの取り組み
ヒヤリハットは、実際に大きなけがや重大な事故が発生する一歩手前の状況です。ヒヤリハットが起きた際、何の対策もせずにそのまま放置してしまえば、重大事故が発生する可能性は高まります。ヒヤリハットが起きてしまったら、「事故につながらなくてよかった」と安堵するだけでなく対策が必要です。効果的な取り組みとして、危険予知トレーニング(KYT)の実施、ヒヤリハット報告書の習慣化、デジタルデバイスによる安全管理があります。
1.危険予知トレーニング(KYT)の実施
危険な状況に陥ってから回避しようとしても手遅れになっていることが多く、対応も難しくなります。そのため、危険な状況になる前に、危険を察知する能力を高めようという考え方があります。危険察知能力を高めるために行われるのが危険予知トレーニング(訓練)です。「危険(K)」「予知(Y)」「トレーニング(T)」の頭文字を取って「KYT」と呼ばれています。
基本的なKYTのひとつである「KYT基礎4ラウンド法」では、以下の手順に沿ってチームごとに話し合いながら進めます。
- 1ラウンド:事実(どのような危険が潜んでいるのか)を把握する
- 2ラウンド:本質(何が危険を招くのか)を追求する
- 3ラウンド:対策を立てる(事故を発生させない方法には何があるのか)
- 4ラウンド:目標を決める(事故を発生させないための施策を実施する)
業務にどのような危険が潜んでいるのかを洗い出したら、それぞれの危険に対処する方法を話し合い、具体的な施策を決め、実際に取り組むべき目標を設定します。目標は全員で共有し、通常の業務内でも指差し唱和などを定期的に行って、一人ひとりの危険察知能力を高めることが目的です。
2.ヒヤリハット報告書の習慣化
万が一ヒヤリハットが起きてしまったら、報告書を作成し、状況を客観的にまとめておくことが重要です。ヒヤリハット報告書を作成する際には、必ず5W1H(誰が担当した、いつ発生した、どこで発生した、どのようなヒヤリハットが発生した、なぜ発生した、どのように対応した)を盛り込みます。
さらに重要なのは、ヒヤリハットが発生した場合に報告書を作成する習慣を定着させることです。似たような事例が二度と起きないようにし、従業員の安全意識を向上させるために、事例や対策法を共有して、重大事故を未然に防ぐ取り組みを進めます。
3.デジタルデバイスによる安全管理
近年では、ヒヤリハットの発生防止や、発生した際には対応策を実施するために、スマートフォンやスマートウォッチなどのウェアラブル端末を利用した安全管理ソリューションが提供されるようになってきました。ウェアラブル端末であれば、各作業者の行動足跡や現在位置、さらにはバイタル(脈拍、呼吸、血圧、体温)を把握・記録できます。工場内に異常が発生した際にウェアラブル端末に通知したり、作業者Aになんらかの異常が発生した際に作業者Bに通知したりすることが可能です。
さらに、工場内で発生した異常は、クラウドを通じて遠隔地の管理事務所などにも通知されます。各作業者のバイタルが数値として把握できるため、本人では気づきにくい異常のサインも見逃さず、休憩指示を出すことなどが可能です。
成果をともなうヒヤリハット報告の進め方
ヒヤリハットは、一歩間違えば重大な事故を引き起こしかねない事象です。放置せず次の3ステップに沿ってヒヤリハットの再発防止に努めることが重要です。
報告書は速やかに作成
ヒヤリハットを経験した従業員には、記憶が鮮明なうちに報告書を作成・提出してもらうようにします。
法的な提出義務や保管義務はないものの、事故予防策を検討する際に必要です。そのため、ヒヤリハットの発生した状況が第三者にも正確に伝わるような、わかりやすい報告書を作成してもらいます。
わかりやすい報告書を作成する際に重要なのは「客観的かつ詳細な記述」「専門用語や略語は使わない」の2点です。ヒヤリハットにおける5W1Hを踏まえて報告書を作成すれば、事実や経緯が明確になります。誰もがフォーマットに沿って報告書をまとめられるよう、あらかじめ5W1Hを踏まえた報告書のテンプレートを用意しておくことをおすすめします。
振り返りと分析で原因を明確に
報告書が提出されたからといって、同じようなミスが減るわけではありません。報告書から「なぜヒヤリハットが発生したのか」を振り返り、その原因を分析して対策を立てましょう。
振り返りで大事なのは、先入観や思い込みを捨てて、事実の把握に主眼を置くことです。報告書を精査し、客観的かつ冷静に5W1Hの部分に焦点を当てて読みます。ヒヤリハット発生のプロセスが整理できたら、原因の分析をはじめます。ヒヤリハットの発生原因は必ずしもひとつとは限らず、多角的に分析することが重要です。
「機械や作業環境に起因しているか」「手順に問題はないか」など、ヒヤリハットの原因を明確に特定し、その後再発防止策を策定します。この際、「関係者の不注意」だけで終わらせるのではなく、事象の根本的な原因や真の要因を追求する必要があります。
対策の周知・追跡評価で再発防止
振り返り・分析から導き出した原因を踏まえ、いよいよ対策を考えます。従業員から改善案を募る方法もありますが、すべてを従業員まかせにはせず、必ず責任者主導で立案します。対策が決定されたら、職場の関係者全員に適切に伝え、速やかに実施することが重要です。実施を遅らせたり、情報共有が不十分だったりすれば、同じ問題が再び発生する可能性があります。
この時点での対策はあくまでも仮説に過ぎず、後に有効性が確認されなければ、再発防止策としての意味があると評価できません。効果が得られない場合、分析と計画の再試行が必要です。
ヒヤリハット報告を「ネタ切れ」といわせない工夫
ヒヤリハットの報告書は、重大な事故を未然に防ぐために必要不可欠です。しかし、単に報告を義務付けるだけではマンネリ化し、おざなりになってしまいます。そのための対策として、勤務時間内に書かせる、報告書を作成するメリットを明確にする、前向きに報告を受け止める、手書きではなくシステムで作成する、といった工夫が必要です。
勤務時間内に書かせる
報告書を作成するにも時間が必要です。自発的な報告が減る、報告書の内容がいい加減になるといった事態を防ぐためには、必ず勤務時間内で報告書を作成することをルール化する必要があります。例えば「退勤前の15分はヒヤリハット報告書作成の時間」と決めてしまう方法もあります。
報告書を作成するメリットを明確にする
ヒヤリハットは人為的なミスによって発生すると思われがちであり、自分の不利益になりかねないと、報告書の作成を怠る従業員がいるかもしれません。ヒヤリハット報告書の作成に関しては、人事上の不利益がないことを明言し、あわせて報告書を作成するメリットを提示します。たとえば、「ヒヤリハット報告を提出した従業員を高く評価する」ことや、「優れたアイデアを出した従業員には報奨金を提供する」など、人事評価や報奨金制度と結びつける施策は効果的です。
前向きに報告を受け止める
ヒヤリハット報告書を提出したものの、その後、工場内でどのように役立てられたのかがわからなければ、報告書を作成した従業員の意欲は削がれてしまいます。ヒヤリハット報告書を精査するだけでなく、報告書が工場内のどの改善に貢献したのかを説明するなどフィードバックを行うことが必要です。
ヒヤリハット報告書が提出された際には、まず当事者に感謝の意を伝え、当事者(報告者)の安全を確認するようにします。決してヒヤリハット事例を発生させたことを叱ってはいけません。ヒヤリハット報告書は工場内の安全性を高める貴重な資料です。万が一ヒヤリハットを発生させてしまった場合であっても、作業者が前向きな気持ちで報告書を提出できる環境を整えておくことが重要です。
手書きではなくシステムで作成する
従来は手書きによる報告書の作成が一般的でしたが、システムを利用すれば容易に報告書を作成できます。あらかじめ記入項目が決められたテンプレートを作成して、簡単に作成・共有できる仕組みを整えましょう。ヒヤリハットが「どこで起きたか」「いつ発生したのか」などの項目を選択式にすれば、記述の手間も省けます。
報告を受ける側にとっても「手書きと違って誤読のおそれが少ない」「記載すべき内容が決まっているので分析しやすい」といったメリットがあります。ヒヤリハット報告書をはじめとした自己報告書の類は、蓄積された情報が多いほど、多角的で高度な分析を行えるようになります。習慣化させるためにも、効率的かつ簡単に報告書を作成できるようにします。
SAFEMO安全見守りクラウドサービスによる安全管理の方法
ヒヤリハットを防止する方法として、デジタルデバイスやクラウドサービスの利用が有効であることは前述した通りです。ここでは、クラウドサービスの例として、富士フイルムデジタルソリューションズ株式会社の「SAFEMO安全見守りクラウドサービス」を紹介します。
「SAFEMO安全見守りクラウドサービス」は、インターネットの通信環境を整備し、工場で働く従業員にウェアラブルウォッチ(スマートウォッチ)を配布すれば、作業現場の様子をリモートで確認できるサービスです。クラウドサービスのため、社内に新たにサーバーを導入したり、システムを構築したりする必要はなく、作業者がスマートフォンを携帯する必要もありません。作業者の体調管理や安全管理、転倒対策、さらには熱中症対策に利用できます。オリジナルのウォッチアプリを開発することも可能です。
作業者に装着してもらうウェアラブルウォッチは、現場の通信環境にあわせて4G通信(eSIM)タイプと、Bluetooth & Wi-Fiタイプの2種類の通信方式から選択できます。重量は30g(4G)または41g(Bluetooth)と軽量で、IP68クラスの防塵・防水性能を備えています。
「SAFEMO安全見守りクラウドサービス」で特におすすめできる点は、ヒヤリハットを減らすための体調管理や安全管理のほか、転倒検知で被害の拡大防止にも対応していることです。
ヒヤリハットを減らす体調管理
本人や管理する上司がいくら気にかけていても、工場内で業務にあたっている作業者の体調を正確に管理することは簡単ではありません。例えば、作業者に対して「昨夜はよく眠れたかどうか」などと上司が尋ねたとしても、その場の雰囲気や回答する作業者の主観によって答えは変わってくるため、必ずしも体調を正しく把握できるとは限りません。
ウェアラブルウォッチが手首に装着されていれば、推測値ではあるものの、作業者の心拍数がリアルタイムでわかります。作業者の体調管理に役立つとともに、体調不良に起因するヒヤリハットを防ぐことも可能です。
ヒヤリハットを減らす安全管理
例えば、製造工場内の装置が故障したなどの異常が発生した場合には、遠隔地で管理しているオフィスに通知されるとともに、工場内の作業者のウェアラブルウォッチにも通知されます。異常が発生している装置に誤って近づくおそれがなくなり、安全を確保できます。
転倒検知で被害の拡大防止
例えば、ウェアラブルウォッチを装着している作業者が工場内で転倒したとします。GPSが異常を感知し、別の現場にいる現場リーダーのウェアラブルウォッチに、作業者が転倒した可能性があることと、作業者の位置情報を通知します。同じ情報は遠隔管理しているオフィスにもリアルタイムで通知されるため、救急車を呼ぶなどの対応が可能です。
ウェアラブルウォッチを装着していれば、作業者の動線の履歴も記録されます。ヒヤリハットが発生する可能性の有無を分析できるだけでなく、無駄な動線を改善して業務効率化につなげることもできます。熱中症で倒れるなどした場合にも、別の現場やオフィスへ即通知されるため、すばやく救命処置を行えます。
4GウェアラブルウォッチmSafetyのご紹介
「SAFEMO安全見守りクラウドサービス」の導入を検討しているのであれば、4G LTE通信が可能なウェアラブルウォッチ「mSafety」がおすすめです。4G LTE接続なので通信可能範囲が広く、工場内のどこにいても作業者の体調・安全管理を行えます。一度充電すれば24時間使えます(通信間隔や使用環境によって変動)。心拍数や加速度を測るセンサーにより作業者の状態をリアルタイムで通知するほか、万が一の際にはSOSボタンで緊急対応を要請することも可能です。IP68クラスの防水・防塵機能を備えており、製造現場にぴったりのデバイスです。
まとめ
ヒヤリハットは、工場内の安全を確保するために欠かせない重要な情報です。幸い重大な事態に至らずに済んだとしても、考えられるリスクを把握し、事故防止策を取ることが大切です。そのためには、KYT、ヒヤリハット報告書の習慣化、デジタルデバイスによる安全管理が重要です。特にデジタルデバイスによる安全管理では「SAFEMO安全見守りクラウドサービス」の導入が有効です。安全な作業環境を保つためにも、導入の検討をおすすめします。